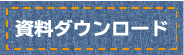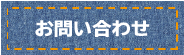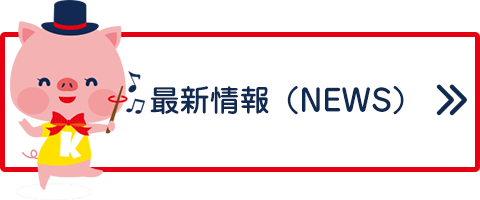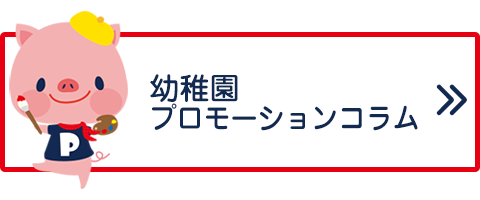メーカーにおけるマーケティングの課題や課題解決策

メーカーは、製品を設計・開発・生産することが中心と思われがちですが、市場での競争が激化し、顧客ニーズが多様化するなかで、マーケティングの重要性が急速に高まっています。
従来は製品の技術力や品質だけで勝負できていた分野でも、新興企業や海外企業の参入、デジタル化の波により、単に「いい製品を作る」だけでは市場をリードするのが難しくなっています。
そこで本記事では、メーカーにおけるマーケティングの役割を整理しつつ、現状と課題、具体的な仕事内容を明らかにします。さらに、メーカーが陥りがちなマーケティング上の問題点を洗い出し、それを解決するための戦略や体制作り、具体的な施策例を紹介します。
メーカー独自の視点や長所を活かしながら、新しい顧客との接点を創出し、市場で優位に立つためのヒントが得られる内容をまとめましたので、ぜひご一読ください。
メーカーにおけるマーケティングの役割
メーカーのマーケティングは、製品の開発・製造だけでなく、市場や顧客に向けてその価値を的確に伝え、販売促進につなげる重要なプロセスです。技術力や製造力が強みであったとしても、適切なマーケティング施策を行わなければ、その魅力を十分に伝えられないまま競合に埋もれてしまう可能性があります。
メーカーのマーケティングの現状と重要性
市場環境が大きく変化するなか、メーカーは従来の「ものづくり」の強みだけでは勝てなくなっています。ユーザーのニーズを正確に捉え、製品企画や販売戦略に反映しなければ、新規顧客を獲得するのは難しいです。
特に、BtoBの取引が多いメーカーにおいても、近年はデジタルマーケティングが重視され、オンラインでの情報発信やリード獲得が主流になりつつあります。
また、人口減少や海外メーカーとの競争激化により、国内だけでなく海外展開が求められるケースも増えています。これらの状況を踏まえ、マーケティング部門の存在意義は高まり、経営戦略と一体となって市場でのポジショニングやブランド構築を行う必要性が強く認識されています。
メーカーにおけるマーケティングの仕事内容
メーカーにおけるマーケティング担当者の仕事は多岐にわたります。製品開発や市場調査、営業企画など、企業のバリューチェーン全体に関わる重要な業務が含まれます。ここでは代表的な業務をいくつか紹介します。
市場調査
新製品を開発するうえでも、既存製品を改良するうえでも、まずは市場ニーズや競合動向を正確に把握する必要があります。マーケティング担当者は、国内外の市場トレンドや顧客の購買行動をリサーチし、収集したデータを分析して企業の意思決定に役立てます。
具体的には、アンケートやインタビュー、公開情報のリサーチなどを活用するほか、近年ではSNS上の声やビッグデータの解析によるニーズ発掘も重視されています。
プロジェクトの立案
市場調査の結果をもとに、新製品の開発や既存製品のリニューアル、キャンペーンの企画などのプロジェクトを立案します。製品コンセプトの策定からターゲット顧客の設定、リリース時期や価格戦略などを決める段階で、研究開発部門や営業部門、製造部門と連携しながら進めることが求められます。
また、海外展開を視野に入れる場合は、各国の規制や文化的背景なども考慮し、プロジェクトの方向性を調整していきます。
営業企画
メーカーが卸売業者や小売業者に製品を提供する際、あるいは直接エンドユーザーに販売する際にも、営業活動を円滑に行うための企画やサポートが必要です。営業資料の作成や販売促進ツールの開発、販売チャネルの選定などは、マーケティング担当者が中心的に動く領域です。
営業担当が顧客と接触する前後で、どのような情報を提供し、どうフォローアップすれば成約率が上がるかを考えるのが営業企画の重要な役割です。
広告・宣伝
製品やブランドの認知度を高めるための広告・宣伝活動もマーケティングの大切な仕事です。テレビCMや新聞広告といったマスメディアから、検索広告(リスティング)やSNS広告、展示会やイベントなど、多岐にわたるチャネルが存在します。
限られた予算や人員を有効に活用するために、ターゲットや目的に最適な媒体や手法を選択し、実行効果を測定しながら改善を行うPDCAサイクルが求められます。
メーカーにおけるマーケティングの課題
メーカーがマーケティング活動を行うなかで、多くの企業が共通して抱える課題があります。技術力や製造力が強みの一方で、市場や顧客との接点作りにおいて苦戦しがちな点はどのようなものなのでしょうか。ここでは代表的な課題を3つ挙げます。
課題1:製品志向が強く顧客視点が欠けている
メーカーは高い技術力を誇る反面、「いい製品を作れば売れる」という製品志向に陥りがちです。その結果、市場のニーズとややズレた製品を作ってしまったり、ユーザーが本当に欲しているメリットを訴求しきれなかったりする場合があります。
特にBtoBの企業では、技術的な優位性を語る一方で、顧客企業が抱える課題や予算、意志決定プロセスを深く理解しないまま提案し、成約につながらないことも。顧客視点をマーケティング全体に取り込む仕組み作りが欠かせません。
課題2:販売チャネルや流通構造が複雑
日本のメーカーは、複数の卸業者や代理店を経由して製品を流通させるケースが多く、最終的にエンドユーザーに届くまでのチャネル構造が複雑化していることがあります。
このような多段階流通では、マーケティング活動をどこに向けて行うかが分散し、各段階の顧客情報を収集・分析するのが難しくなるという課題があります。
また、販売店や代理店ごとに提供するサービスや価格が異なり、ブランド統一感やマーケティング施策の一貫性を保つのが難しいケースも見受けられます。
課題3:デジタル対応が遅れている
海外企業やIT系の新興企業はデジタルマーケティングへの適応が早い一方で、伝統的なメーカーでは、デジタル活用への投資や人材が不足していることが少なくありません。
自社サイトのSEOやSNS運用、マーケティングオートメーション(MAツール)の導入など、多岐にわたるデジタル施策を十分に活用できず、顧客データやリードを活かしきれない状況が続いている場合があります。
これにより、オンライン上でのブランド認知やリード獲得において競合に後れを取るリスクが高まっています。
メーカーに有効なマーケティング戦略
上記の課題を踏まえ、メーカーが取り組むべきマーケティング戦略にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、オンライン・オフラインを問わず、有効とされる代表的な手法を概説します。
製品ブランディング
技術力や品質を誇るメーカーにとって、製品のブランドイメージを確立することは大きな価値があります。競合が多い市場で価格競争に巻き込まれないためにも、独自のストーリーやこだわりを明確に打ち出し、「このブランドの製品なら安心」「付加価値が高い」という認識を市場に広めることが重要です。
単に商品カタログで性能を説明するだけでなく、ユーザーが得られる体験やメリットをストーリー仕立てで伝える手法が注目されています。
リスティング広告
GoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワード検索を行ったユーザーに対し、上部や右側に広告を表示する手法です。ユーザーが能動的に情報を探しているタイミングで表示されるため、成約率が高くなる傾向があります。
メーカーの場合、「製品名+価格」「課題解決+製品ジャンル」などのキーワードを中心に設計すると効果的です。BtoBの長期商談には、まずは資料請求や問い合わせを獲得するなど、複数段階での成果指標を設定して運用するとよいでしょう。
ディスプレイ広告
ウェブサイトやアプリの広告枠にバナーなどの画像広告を配信し、潜在的な見込み客にアプローチする手法です。認知度向上やブランドイメージの醸成に適しています。
多くのユーザーに短期間で露出を図る場合や、ビジュアルを活かして製品の魅力を視覚的に訴求したい場合に有効です。
ただし、興味の薄い層にも配信される可能性があるため、ターゲットセグメントの精緻な設定やクリエイティブの魅力が鍵となります。
リターゲティング広告
一度自社サイトを訪れたがコンバージョンに至らなかったユーザーに対し、他のサイトやSNS上で広告を再表示させる技術です。BtoB商材など、商談までの検討期間が長い場合には、検討段階のユーザーに継続的にアプローチできるメリットがあります。
「資料請求ページまで来たが離脱したユーザー」「特定の製品ページを閲覧したが申し込みしなかったユーザー」など、行動データを活用して広告を出し分けると効果が高まります。
SNS広告
FacebookやInstagram、X(旧Twitter)、TikTokなどのSNSで配信される広告は、ユーザー属性や興味関心を細かく設定できるため、製品のターゲットを絞った宣伝が可能です。BtoC向け商品だけでなく、BtoBでも担当者がSNSを利用している場合もあるため、有効なケースが増えています。
製品のビジュアルを活かした動画広告や短いテキスト広告など、各SNSのユーザー行動にマッチした形式で配信すると、認知度向上やクリック率が高まりやすいです。
タイアップ広告
専門メディアやインフルエンサーとのタイアップにより、製品紹介やインタビュー記事を発信する手法です。ユーザーは広告感が薄いため抵抗感が少なく、関連メディアであれば高いエンゲージメントを得やすいメリットがあります。
特に技術系のメディアや業界専門誌などでのタイアップは、BtoB分野における信頼度向上につながる可能性が高いです。
展示会
オフラインでの施策ですが、メーカーが新製品を発表したり、潜在顧客との関係を強化したりするうえで展示会は非常に重要です。実物に触れられるため、製品の性能や使い勝手を直接体験してもらえます。
また、同じ業界の企業や関連メディアが一堂に会するため、情報収集や人脈形成の面でもメリットが大きいです。展示会後のフォローアップ施策(メールや電話での連絡)をきちんと行うことで、成約につながるケースが少なくありません。
ホワイトペーパー
技術的な詳細や導入事例、業界トレンドなどをまとめた文書(ホワイトペーパー)を制作し、ダウンロードフォーム経由で配布する手法です。製品の機能やソリューションを深く理解してもらえるため、BtoBマーケティングでは定番となっています。
ホワイトペーパーのダウンロードと引き換えにユーザーの連絡先を取得すれば、その後のメールマーケティングや営業活動にも活用できます。
セミナー
オンラインセミナー(ウェビナー)やオフラインセミナーを開催し、自社製品や技術の魅力を伝えるとともに、参加者と直接コミュニケーションを取る方法です。信頼関係を築きやすく、専門的な説明が可能であるため、興味度の高い顧客を効率的に獲得できます。
講師に業界の権威や著名人を招くなど、参加者にとって価値あるコンテンツを提供すると、満足度とリピート率が高まりやすいです。
DM
オンラインセミナー(ウェビナー)やオフラインセミナーを開催し、自社製品や技術の魅力を伝えるとともに、参加者と直接コミュニケーションを取る方法です。信頼関係を築きやすく、専門的な説明が可能であるため、興味度の高い顧客を効率的に獲得できます。
講師に業界の権威や著名人を招くなど、参加者にとって価値あるコンテンツを提供すると、満足度とリピート率が高まりやすいです。
メールマーケティング
見込み客や既存客に対して、定期的にメールマガジンやキャンペーン情報を配信する手法です。低コストで大量配信が可能であり、クリック率やCV率などの数値分析も容易です。
ホワイトペーパーのダウンロードや展示会の名刺交換などで取得したリストを活用し、顧客の興味関心に合わせたパーソナライズドな内容を送ることで、商談化の可能性を高められます。
マスメディア広告
テレビCMや新聞広告、雑誌広告など、伝統的なマスメディアを活用する方法です。費用が高額になりやすいものの、短期間で一気に多くの人々へ訴求できるメリットがあります。特に消費財や知名度重視の製品であれば、マス広告によるインパクトは依然として大きいです。
ただし、ターゲット層が絞り込みにくいため、反響を正確に測定しづらいというデメリットもあります。
メーカーにおけるマーケティング課題解決案
多様な戦略や施策があるなかで、実際にメーカーが抱えている課題をどう解決していくかが重要です。ここでは、組織体制の整備から外部リソースの活用、認知度アップのための工夫など、課題を解決するための具体的なアプローチを紹介します。
マーケティング部門を体制を整える
まずは社内にマーケティング専任の部門や担当者を設け、権限と責任を明確にすることが重要です。製品企画や営業企画、広告宣伝など、企業内の複数部署にまたがる業務を統括できるリーダーやチームを置くことで、横断的な情報共有と素早い意思決定を実現します。
また、デジタルマーケティングの知識を有する人材や、外部と連携できるコーディネーターを配置すると、組織内にノウハウが蓄積され、施策の効果やPDCAを回す精度が上がるでしょう。
マーケティング支援会社に依頼する
社内リソースや専門知識が不足している場合は、広告代理店やコンサルティング会社など、マーケティング支援の専門企業に部分的または全体的に業務を委託する方法があります。
たとえば、デジタル広告の運用やSNSマーケティングを外部に任せつつ、製品コンセプトやブランド戦略は社内で決定するといったハイブリッドな形も有効です。コストはかかりますが、短期的に結果を出したい場合や専門性が必要な施策に向いています。
自社製品の認知度を上げる方法を模索する
国内外の展示会に積極参加する、オンラインセミナーやWebメディアのタイアップで新製品を紹介する、業界専門誌に広告や記事を掲載するなど、多様なチャネルで製品を露出する工夫が求められます。
特にメーカーの場合、実際に製品を見たり体験したりしないと価値が伝わりづらいケースが多いため、デモンストレーション動画や体験イベントなどを通じてユーザーに直接触れてもらう機会を作ると効果的です。
マーケティングミックスを活用する
製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)といった4Pを軸とするマーケティングミックスの考え方は、メーカーでも非常に重要です。
技術力や品質を自慢するだけでなく、市場に求められる価格設定や販売チャネルの選定、効果的なプロモーション手法の組み合わせを検討し、最適解を導きます。
また、BtoBの場合は「ソリューション提供」「アフターサポート」などの要素も加味した上で、クライアント企業が抱える課題を的確に解決できる形を探ることが大切です。
広告運用時のガイドラインを敷いておく
リスティング広告やSNS広告など、企業イメージを左右する広告手段を複数運用する場合、ブランドイメージや製品メッセージが一貫性を持つようにガイドラインを設定しておくべきです。
色使いやロゴの扱い、許可されたコピー表現、個人情報保護などのルールを明確化し、社内外の関係者と共有することで、コンプライアンスリスクやメッセージのぶれを防ぐ効果があります。
特にグローバル展開を行うメーカーなら、各国の言語や文化に合わせてガイドラインをローカライズする対応も必要でしょう。
製品の質だけでなく”如何に届けるか”も重視される時代に
メーカーはものづくりの高い技術力を持っている一方、市場が成熟し競合が激化する現代では、マーケティング力の差がビジネス成果を大きく左右します。
市場調査やプロジェクト立案、広告・宣伝といった多方面の業務を担うマーケティング部門が活躍しなければ、自社製品の魅力を十分に伝えられず、他社に埋もれてしまうリスクが高まります。 メーカーにおけるマーケティングの課題には、製品志向が強いために顧客視点が欠けることや、複雑な販売チャネル、デジタル化への対応遅れなどがあります。
これらを解決するためには、マーケティング組織の強化や外部の専門家の活用、認知度を高めるためのブランディング施策や広告手法などを総合的に組み合わせることが重要といえます。 デジタル広告やSNS、ホワイトペーパー、セミナーなど多様なチャネルを活用する一方、展示会やDMといったオフライン施策も組み合わせることで、幅広いターゲットにリーチできます。
さらに、マーケティングミックス(4P)の視点から製品価値と価格、流通経路、プロモーションを最適化し、広告運用のガイドラインや体制を整備していくことが、メーカーの今後の成長を後押しする大きな要素となるでしょう。
他にも幼稚園・保育園イベントや幼稚園・保育園モニタリングを行っているのでぜひご覧ください。

株式会社エンジン
代表取締役 常盤 亮太
世の中の原動力となるような会社にしたい。
その想いから社名を「エンジン」と名付けました。
また、人と人の縁を大切にし、仁義を重んじること。
そして、円陣が組めるくらい、そんな人間の集団を創っていくこと。
そんな想いも込めています。
当社では、企業=人という考え方が根底にあります。
世の中の原動力となるような会社は当然ですが素晴らしい企業であり、
素晴らしい企業であれば、素晴らしい人間の集団であると思っています。